知らなかった!割栗石の歴史と現代の利用方法
割栗石は、建築や土木工事において非常に重要な素材の一つです。
本記事では、割栗石の歴史や利用方法について詳しく解説します。
割栗石の背景を深く理解しましょう。
割栗石の起源
割栗石の歴史は非常に古く、その名前は古代から栗石を割って使用してきたことに由来します。
古代ローマの遺跡や古代エジプトのピラミッドの建設にも割栗石が使用されていることが確認されており、その耐久性と安定性が高く評価されていました。
これらの歴史的事実から、割栗石が古くから重要な建築材料として利用されてきたことがわかります。
割栗石の伝統的な用途
建築基礎工事
割栗石は主に建築物の基礎工事に使用されてきました。
基礎の下に敷き詰めて地盤を安定させるために長年利用されています。
特に「割栗地業」と呼ばれる工法では、割栗石を小端立てにし、上下を楔状に交互に敷き込み、目潰しや上端均しのために切り込み砂利を用いて突き固める方法が伝統的に行われてきました。
城郭建築での利用
日本の城郭建築でも割栗石は重要な役割を果たしてきました。戦国時代の城郭内の城門や建物、神社仏閣などで割栗石が使用されていたことが、現代の調査でわかっています。
近代以降の割栗石の利用
建築基礎工事以外
割栗石は、明治、大正、昭和初期までは道路や塀、垣などの基礎工事にも広く使用されていました。しかし、第二次世界大戦後の復興期からは、コストと工期の面で優位性があるコンクリートが大量に使われるようになり、特に住宅建築での割栗石の使用は減少しました。
現代の建設プロジェクト
現代においても、都市開発やインフラ整備が進む中で、高層建築や高速道路などの建設プロジェクトで割栗石が重要な役割を果たしています。その耐久性と安定性が評価されているためです。
割栗石の規格化
日本産業規格(JIS)によって、割栗石の原石の種類や大きさ、形状が規定されています。各砕石業者では50-150mm、150-250mmのサイズで作られていますが、JIS規格では一個あたりの重さで決められており、1号割栗石は10kg±2kgとなっています。他にも2号、3号、5号、10号、20号、30号、50号、70号、100号までの規格があります。
現代の割栗石の利用傾向
小規模な住宅建築
最近の民間工事では、ベタ基礎の普及により、小規模な住宅建築では割栗石を使用しない傾向が見られます。しかし、伝統的工法として一部の工務店が採用しているほか、外構やエクステリアのデザイン要素としても人気が高まっています。
割栗石を用いたデザイン
2000年初頭から、庭師が割栗石を使った庭のデザインを始め、そこから庭に装飾的に使うというデザインが広まりました。これにより、割栗石は現代でも注目されるようになりました。
まとめ
割栗石は、日本の建築や土木の歴史において長く重要な役割を果たしてきた素材です。その用途は時代とともに変化していますが、現代においてもその価値は続いています。伝統的な建材としての役割に加え、外構やエクステリアのデザイン要素としての可能性も広がっています。
割栗石の歴史と利用方法を理解することで、その魅力を再発見し、現代の建築やデザインに生かすことができます。
約8400m2ある石置場には、様々な色•大きさ•形の石を全国から集めて、展示しています。
DIYで庭作りされる素人のお客さん•庭師•工務店•外構屋•インテリア•店舗•花屋•設計事務所等のお客さんが、石を使ったおしゃれな庭を作られています。
#揖斐川庭石センター
line(ライン)を使われてる方は、ぜひ、弊社の公式LINE公式アカウントに「友だち登録」して、気楽に問い合わせしてみてください。
・スマホ、ケータイを使って、いつでもどこでも周りを気にせず、リアルタイムで1:1の問い合わせのやり取りができる。
・問い合わせで文字では説明しにくい時は、スマホ、ケータイで撮った現場や庭、家の画像を送ることができるので、スムーズにやり取りできる。
・弊社の商品や施工事例、日々の出来事などの情報がタイムラインで見られる。
よろしければ、「友だち追加」をタップ・クリックか、QRコードを読み込んでください。↓
Email
メールでのお問い合わせ
Instagram
ほぼ毎日、仕事ぶりを更新
LINE公式アカウント
LINEでお問い合わせ、公式lineアカウント限定の記事書いてます
Twitter
どうでもいいつぶやき
YouTube
たまに、動画載せてます
Facebook
ほぼ毎日、仕事ぶりを更新
Profile
自己紹介










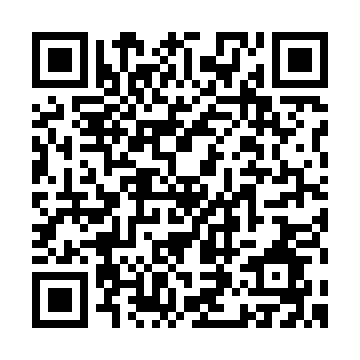



「栗石」とは、その大きさにある様な小さいかサイズにのみ使われるとみなしてますが、実は他にも用途はあって、「丸み」が基本的な特徴を表しますが、ここで紹介されてる定義はあくまでも近世的な解釈が問題を呈してます。その利用用途が城郭の基礎材として挙げられてますが、それは稚拙すぎます。特に館や城郭、或いは城の役割をもつ仏閣での「庭園技法」に関係することを見逃してるようです。その役目とは何かといえば、出入りができる敵方の侵入を門や裏門に限定されると言えるのかという点にあっては、その屋敷や城、仏閣の『庭』からの侵入も当たり前に考えられていたことを見逃してはなりません。その際に騎馬での侵入と徒士武者による侵入を防ぐ為に庭の中に2メートルから1メートルサイズの『栗石』が置かれます、つまり、庭を横切る際に真っ直ぐに突入進行できないように設置される。また、馬首を、踵を返す事ができないようにして置かれます。馬の体をねじれない、捩ることが不可能なのですね、これがですね、そのあぐねてる好きに槍や弓で急襲される、いわゆる防備対策で使う工夫に置き石として丸い石が使われる。また、その敵方の急襲は夜間に行われる為に『栗石』は真黒なものが選ばれます。新月などの闇夜にあっての急襲の際にその黒色が敵兵の目には確認が難くて防備する方には大いに役立つ。実際に900年ほど昔からある屋敷の庭石の配置図が当家には残されてます。また、『栗石』の名も記されてます。現在その庭は廃棄されていて現物は残ってませんが屋敷図はあります。真っ黒なので何処が産地なのか不明です。その古式の庭での『栗石』の利用がある事をお伝えします。